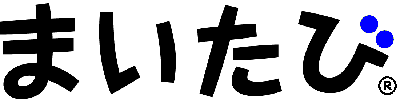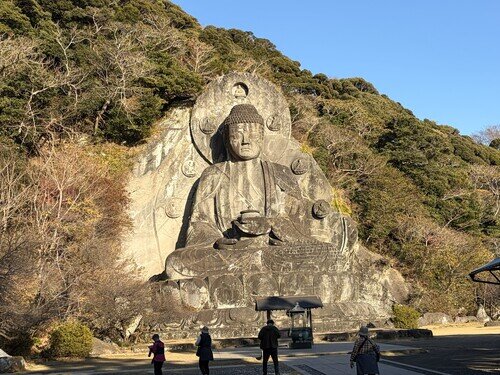富士山の五合目に立つと山頂は意外と近そうに見える。
しかしながら、吉田ルートの五合目から山頂までの距離は7キロもある。富士山という山は、意外と大変な山である。
今年から五合目に新たにゲートができた。関所をイメージしたというその姿は、威圧感さえあった。ゲート前に立つ警備員の方はよく見かける現代の服装だが、この人たちが江戸時代の服を着ていたらまさに昔の関所そのものだろう。それもそのはず、このゲートは江戸時代の関所をイメージして作られたのだ。
3月から富士山登頂を目指してきた参加者は今日が富士山本番。低い山から少しずつ難易度を上げながら登山の基本的な知識を学び、実際に山を登ることで経験を積んできた。天気は快晴。風も弱く絶好の登山日和。
 バス車内でも登山口でもしっかりとしたアドバイスが2名の登山ガイドから参加者には与えられた。
バス車内でも登山口でもしっかりとしたアドバイスが2名の登山ガイドから参加者には与えられた。
五合目を出発して六合目までは緩やかな登り。時折開ける左側の景色は、富士吉田の町や河口湖、そして山中湖、丹沢や道志の山々だ。六合目に到着した時にはややガスに覆われていた。雨が降るような予報ではないので、逆に少し涼しく登らせてもらえるのでありがたい。


細かい石が混じる砂浜のような登山道を、呼吸を整えながらゆっくりと登る。
呼吸のリズムもガイドから丁寧にアドバイス。吸い込むことよりも息を吐くことを意識する。そうすれば自然と酸素が取り込める。一定のペースで登ることが高所では何よりも大切なこと。背後には高所を実感させる見事な雲海が広がる中を登る。見上げればつづら折りで続く登山道と山小屋。こんなに山小屋が連なる山はない。富士山ならではの光景だ。


 七合目からは溶岩の上を登る。ごつごつして不規則な形の登山道は登りやすいとは言えない。むしろ登りにくい。これが八合目の半ばまで続く。
七合目からは溶岩の上を登る。ごつごつして不規則な形の登山道は登りやすいとは言えない。むしろ登りにくい。これが八合目の半ばまで続く。
この溶岩道の途中、七合目が初日の宿だ。大きな宿ではないが、歴史ある老舗の日出館。
宿に到着してもガイドから大切なアドバイス。それは、すぐに横になって寝てしまわないこと。寝ると呼吸が浅くなり、高山病になりやすい。だからしばらくはおしゃべりをしたり、散歩をするなどして過ごすことが高所への順応を高めて高山病の予防になる。
寝床の前にあるスペースで夕食を済ませ。夕陽に雲が染まるのを待ったが、ドラマチックな夕焼けにはならなかった。はるか眼下には富士吉田の街明かり、そしてもっと遠くには東京や埼玉新都心の夜景が見えた。夜が更けるにつれて街の明かりは強さを増していった。明日の日の出に期待しよう。
2日目。この日はいよいよ山頂を目指す。日の出前から準備をはじめて出発。歩き始めてから10分ほどで朝日が雲の間から昇り始めた。
真っ赤に輝きながら、ちょうど真ん中あたりに雲の帯をつけた太陽が昇ってきた。望遠でシャッターを切る。お客さんも足を止めて、富士山からの日の出を拝む。日の出が見られたことは登頂への意欲を掻き立てる。

 大沢崩れのような赤い土や石、これが朝日に照らされると赤く見える赤富士の正体。
大沢崩れのような赤い土や石、これが朝日に照らされると赤く見える赤富士の正体。
 呼吸を乱さないように一歩一歩丁寧に、ひとつひとつ山小屋を通過していった。場所によっては山頂が見える。近そうに見えても遠い、それが富士山。
呼吸を乱さないように一歩一歩丁寧に、ひとつひとつ山小屋を通過していった。場所によっては山頂が見える。近そうに見えても遠い、それが富士山。

 山小屋が続く八合目、九合目を過ぎて、白い鳥居が見えてきた。あと1kmもない。ここまで登れればもう山頂を踏めることは誰もが確信できる。風も穏やかで天気が崩れる心配もまったくない。いい条件で登頂できそうだ。
山小屋が続く八合目、九合目を過ぎて、白い鳥居が見えてきた。あと1kmもない。ここまで登れればもう山頂を踏めることは誰もが確信できる。風も穏やかで天気が崩れる心配もまったくない。いい条件で登頂できそうだ。


夏の2カ月ちょっとしか富士山の山小屋は営業しないが、その期間はとても活気がある。夏を感じる光景でもある。逆に9月の上旬を過ぎると小屋は営業が終わり、富士山はとてもさみしくなる。
つづら折りを登り、最後の白い鳥居をくぐって念願の山頂へたどり着いた。
「やったー!」「登った!」
半年近くにわたり、いやそれ以上だったかもしれない。思い憧れてきた富士山へと登ることができた。「あの山がステップ5で登った山」「こっちがステップ3」これまで富士山に登るために経験を積んできた山々を今は上から見下ろしている。全員とはいかなかったが、ほとんどの方が登頂の喜びに顔をほころばせた。
登頂の喜びのまま少し休憩したのち、お鉢巡り(火口を歩いてまわる)に出かけた。私たちのツアーは2泊。行程には余裕があるので、お鉢巡りの時間も心配はいらいない。高所に順応して登頂率を高めるだけではなく、ほぼお鉢巡りもこなせる時間的な余裕がある。体験してみてよくわかる内容ではないかと新ためて感じる。
 天気が崩れるような様子はまったくない。澄んだ真っ青な青空がどこまでも広がっている、山の上で見る空は町中で見る空とは大きさがまるで違う。そんな当たり前のようなことも山に登ると新鮮に感じさせてくれる。五感をフルに楽しませてくれるのである。これこそが山の大きな魅力だと感じる。
天気が崩れるような様子はまったくない。澄んだ真っ青な青空がどこまでも広がっている、山の上で見る空は町中で見る空とは大きさがまるで違う。そんな当たり前のようなことも山に登ると新鮮に感じさせてくれる。五感をフルに楽しませてくれるのである。これこそが山の大きな魅力だと感じる。
最高点の剣ヶ峰は吉田口の山頂のちょうど真反対にあり、トンガリピークとなっているのでわかりやすい。

雲の中に吸い込まれそうな感覚味わいながら火口の縁を歩いていく。お鉢巡りの途中にある郵便局は多くの登山者に人気がある。ハガキを出す方、浅間大社の奥宮でお参りをする方。お鉢は歩くだけではない。
このお鉢巡りで、剣ヶ峰の手前だけがずるずると滑りやすくていただけない。ここを登りきると富士山の本当の山頂である。石の山頂標識はみんなが写真を撮りたがるので、行列ができている。少しずらして、ハイポーズ。
これでも十分剣ヶ峰だ。放射状の雲はファンファーレを形にしたみたいだ。
残り半周を歩き、今度は八合目の宿まで下る。
下山道は、登りとは道がわけられている。小石が滑りやすく、砂ぼこりがたつのでこの道は好きになれない。雨の後ならしっとりとして歩きやすいのだが。
午後になっても不思議なくらいこの日は天気が良かった。ツアーの日に天気がいいと本当に私たちもうれしい。天気がいい仕事をしてくれている。
3日目の朝日も素晴らしかった。真っ赤に雲を染め上げながら太陽は登ってくる。日の出の1時間くらい前から朝のドラマは始まる。マジックアワーと呼ばれる時間だ。
最終日は下るだけ。しかも、余裕をもって下ることができる。

下りで見る景色もまた豪快だ。つづら折りの道を曲がるたびに雲海に向かって歩いていくような景色が広がる。独立峰で高い標高だからこそ味わえる楽しみもしれない。どこまでもどこまでも雲海が果てしない。道は明らかに雲の中に続いていた。


山では自分の想像をはるかに超える景色に会うあることがある。どれだけやってもそんな景色に出会える瞬間がある。
参加していただいた皆様にも、一回でも多くそんな景色を自分の足で確かめてもらいたい。
自分の足で登るからこそ巡り会う景色や普段の生活では味わえない感覚がある。それを山は与えてくれる。
富士山の登頂を通じて、登山を続ける喜びをこの富士山で感じてもらえたら私たちにとっても最高の喜びです。
【文と写真】
渡辺和彦